
クラフトビールのもっとも美しい姿を
美味しさというバトンでリレーする
2023.12.25
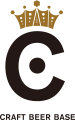
株式会社CRAFT BEER BASE 谷 和 氏
個性豊かなクラフトビールが味わえる、ブルワリーが併設されたブルーパブスタイルが人気だ。造り手が注ぐ一杯は、そのビールが一番美味しい状態を知っているからだ。「同じビールでも味が同じではない」、そんな疑問を持った一人のビール好きが、自ら醸造所を持つまでに至ったのはなぜか、代表の谷氏に聞いた。
INDEX
ビールが好きでも、ビールを知らない
代表の谷氏は、ビールが大好きだ。クラフトビールを知るもっと以前から、お酒を飲むシーンには欠かせない身近な存在だった。飲む人から売る人へ、そして造る人へ、谷氏の業界人生の幕開けは、26歳の頃にさかのぼる。出資をするので店舗を経営してみないかと、飲み仲間から提案されたことがきっかけだったという。
「それなら大好きなビールの店を、と思ったのですが、いざとなるとビールの扱い方がまったくわからないわけです。それなら1年間の勉強期間をくださいと、まずは日本地ビール協会の認定資格であるビアテイスターの取得を目標にすることにしました」

その時の講師に実地で学べる場所はないかと相談したところ、大阪のベルギービール専門店『ドルフィンズ』を紹介された。
「先生がドルフィンズの社長に『今日からこの子を雇ってあげて』と言うと、『いいよ』と、あっという間に決まってしまいました」
時代は第二次クラフトビールブームの初期、2004年の頃だ。そもそも谷氏はどうしてビールを選んだのだろう。
「単純にビールが好きというのもあるのですが、前職はパンを扱う仕事、出身は香川県、香川といえばうどん、すべて“麦”つながりです。理由にならないですかね」
麦から始まる物語、谷氏のビールのプロフェッショナル修行が始まった。
造り手の意思を継ぐ、プロとしての目覚め
ドルフィンズでは、谷氏は未経験ということもあり、当初はグラス洗いや配膳が主な仕事だ。しかし勤め始めて3か月目のことだった。
「社長に、ベルギーに研修旅行に行くからその間10日ほど店を閉店するって言われたんです。はいそうですか、とはこちらもいきません。それなら連れて行ってくださいと、実費でベルギーの研修についていくことにしました」

海外旅行が好きな谷氏にとって、外国での研修に躊躇はなかった。現地では醸造所を巡り、ビールを造る人たちに初めて会うことができた。ビールの種類の豊富さとともに文化の違いを目の当たりにした。
「ビールを注ぐ研修では、本家大御所・デュベル・モルトガット(デュベル)社にあるトレーニングルームでの社長の前で行われました。それまで一度も人前でビールを注いだことなんてありませんし、何よりデュベルビールの正統な注ぎ方には独自のセオリーがあるんです。それをよりによって造り手の社長の前でやることになるなんて…」
研修では水が使われることもあるが、ここでは実際の製品が使われた。見様見真似では通用はしない。綺麗に泡を立てて注ぐ先輩たちを横目に、緊張で腕がガタガタ震える谷氏を、デュベル社の社長が呼んだ。
「デュベル社の社長に『あなたは日本で私たちのビールを注いでいる。私たちは一生懸命ビールを造っているのに、あなたがそんな感じでは、私たちのビールをどうやって日本で美味しいと言ってもらえるんだろう』と、フラマン語で直接はわかりませんでしたが、はっきりと伝わりました」

辛辣だが、信頼しなければ掛けられない言葉だ。造り手として製品という魂を託す相手への激励でもある。
「あなたの手にかかっているのだから、努力をしなさいと言われました。目から鱗が落ちるとはまさにこのことで、ビールに関わるというのは、それを仕事として行うだけではなく、造った人の意思を受け継いで、自分が代表して伝えることなんだと思いました」
帰国後は、サービングの猛練習が始まった。店長に頼んでデュベルの注文は、すべて自分に回してもらった。そんな谷氏を見ていた馴染みの客は、応援の気持ちからデュベルを注文してくれたという。
「デュベル社の社長の言葉にパンチを食らって目が覚めたような気分でした。それからは注ぐことだけでなく、それぞれのビールの歴史や背景も知りたくなったんですね。お客さまに提供する価格には、プロのサーバーとしてのパフォーマンスが原価に上乗せされているわけですから、手を抜きたくなかったんです」
テイスターからジャッジメントとしての責任
谷氏はビールの知識をさらに掘り下げ、ビアテイスターの資格の延長線にあったビアジャッジの資格を取得した。
ドルフィンズでは、アルコール度数が高いものは10℃、エール系は7℃、爽やかさに飲みたいものは5℃と、ビールの特性に合わせて温度管理を徹底していた。谷氏は毎日3本を飲み、ノートにそのときの味わいを細かく記載していた。ノートの書き出しを始めて2年目になる頃、ビールのプロフェッショナルとして経験を積むなかで、あることに気が付いた。

「知識を得て“これぞ本物のビール”といわれるものが、どうも市場で飲まれている味わいと違うなと思ったんです。同じ銘柄なのに、同じ味じゃない。どうしてだろうと突き詰めていくと、同じレシピでも味が変わることがわかって、これは面白いなと。今日のカレーと1か月後に作ったカレーの味は違う、みたいな感じでしょうか」
厳密にいえば、原料の収穫時の気候や醸造時の季節によって味は左右される。その最たるものがワインのブドウに例えられるだろう。
「野菜もそうですが、トマトはトマトでも流通に乗せるとなると規格が必要になります。ビールにしてもその年ごとの変化を楽しむという軸とは別に、品質には数値化した一定のレンジを守ることがプロフェッショナルだと思うんです」
各国の“発祥”といわれるビールには、サービングや品質管理を含めて正統なスタイルが体系化されており、もっとも美味しく飲むための規格が明文化されている。それがビアジャッジの基準にもなっているが、谷氏も自らのビアジャッジの経験のなかで飲んだ正統なビールは、「鳥肌が立つほど美味しい」という。
谷氏がもっとも懸念したのは、製品本来の味が損なわれてしまう要因だ。
「オフフレーバーや流通の過程にある管理などでいろいろな課題があるなと気付いたんです。ただそれを誰も変えようという流れが当時はまだありませんでした。一つのビールを造り手、運び手、売り手、注ぎ手、いろいろな人たちのリレーで美味しさを伝えていく。グラスの中に造り手の言いたい味が届き、初めて価値があると思うんです。造り手と対等に話しができる存在として、ビールを扱うためのプロがこの業界には必要だと決意しました」
あなたが本当にしたいことは何ですか?
「これはもう天職や!」と、ますます仕事にのめり込んでいく折り、谷氏は結婚し、そして出産をすることになる。
「夫は私が勤めていたドルフィンズの店長と仲が良い常連で、ほぼ毎日のように最後までお店で飲んでいました。いつも彼は店を閉めてから店長と食事していたのですが、そこに私も誘われるようになったのが結婚のきっかけです」
結婚前にベルギービールの研修にも同行したというご主人、それからの谷氏の人生の“スイッチ”を押すキーパーソンとなる。

産休、育休を経て、ドルフィンズに復帰するが、乳児を育てながら飲食店のシフトに対応するには無理があった。
「職場の皆さんはとても優しいのですが、むしろ私自身が本領を発揮できないことに居心地の悪さを感じてしまったんです。1年後に思い切って転職することにしました」
夕方5時に帰宅できることを最優先に、次に選んだ仕事は、弁護士秘書だった。半年間ほど専門学校に通い、首席で卒業したというから驚きだ。引く手あまたのなか、老舗の事務所に入ったが、職場の雰囲気に馴染めず、半年後にコンサルティング会社の社長秘書に転職した。
「主に企業の経営層を対象にしたビジネスコンサルで、女性の社長はいつも顧客に対して“あなたは何をしたいのか”をテーマに話していました。やがて私も『谷さんが本当にしたいことは何でしょう』と聞かれるようになったんです」
そのときの谷氏は、子どもが小さいことを理由にビール業界への復帰を諦めていたという。ただ、“あなたは何がしたいのか”という言葉が呪文のように頭の中を巡り、まずは何か始めようと、個人的にビールのイベントを開くことにした。

「私をドルフィンズに紹介したビアテイスターの先生、私は師匠と呼んでいますが、彼女が人脈を使ってイベント告知をしてくれました。会議室や酒屋さんの2階を借りて、3か月に1度のペースで開催していました」
まさに水を得た魚だろう。谷氏はビールのイベントが楽しくなる一方で、本業との気持ちのバランスが崩れていくのを感じていた。
「夫にどうしたらいいかと愚痴混じりで話すと『そんなに悩むなら(ビールの仕事に)戻ったら?好きなことやったらええやん』と言われたことで決心がついて、社長に思いを伝えました。やっぱり私、ビールが好きです、と。社長は『いまの谷さんはビールに心が持っていかれて、ここの仕事ができなくなっちゃってる。それなら自分のやりたいことに集中しなさい』と。まるで有名なバスケットの漫画みたいでした。泣きながら『先生、私、ビールの仕事がしたいです』って。」
ビールの職場から離れて1年後、2009年のことだった。
正論を話すだけでは人は動かない
満を持して社長秘書の仕事を辞め、酒屋やインポーターと呼ばれる輸入業者など、いざビールに関わる会社へ履歴書を持って回ったが、なかなか職場が見つからない。そんなある日、考えあぐねていつもの買い物ルートとは違う方向に歩いていると、一軒の酒屋の裏手に、ベルギービールの空き瓶が山のように置かれていたという。
「業務卸専門店で、ラインナップが一般的な酒屋さんのものじゃなかったんです。勇気を出して引き戸を開けると、ちょうど事務職の欠員が出たというので、その場で採用が決まりました」
自宅から徒歩5分、灯台下暗しとはこのことだろう。願ったりかなったりとさっそく働き始めたが、当時の流通の実態を知って愕然とした。
「日本酒、ビール、洋酒、焼酎と、仕入れた酒の倉庫はそれぞれあるのですが、すべて保管は常温なんですね。どんなに高級なシャンパンでも同じです。とくにかく驚いて、社長に何度か提案やお願いをしたのですが、相手にしてもらえませんでした。他の出入り業者さんにも話しましたが、当時はそれが業界の“当たり前”だったんです」
そのとき谷氏は、話を聞いてもらうだけでは誰も動かない、自分でやって証明しなければ流通は変わらないと思ったという。そうは言え、主婦の立場や子どものことを考えると、起業するには躊躇がある。
「夫に職場のことを話して、でも子どもが、お金が、と、ずっと愚痴を言っていたのですが『うるさいわ!そんだけ愚痴を言うんやったらもう自分でやれ』と言われて…。お金も貸してくれて、もうやらざるを得ない状況になりました」

流通を正したいという一心で、酒販業の免許を取りに税務署を訪ねたが、時代は酒の量販店が勢いを増していて、個人の酒販業の事業計画では、「前例がない」という理由で交付には至らなかった。そんなときに赴いた東京で、1階がワインの酒屋、2階がレストランという店舗を見かけた。
「1階で買ったものを、上のレストランに持ち込めるスタイルで、制限はあるものの、売上を上げるにはこれだと思いました。どうやったらそのビジネスモデルが実現できるのか、税務署で相談したところ、一緒になって考えてくれました」
並行して準備していた物件探しにも難渋した。店舗経営の経験もなく、資金もあまりない、小さな子どもがいる女性となると、なかなか契約はしてくれない。
「探しに探した末に一軒の古い民家を紹介して頂いて。小さな間口でしたが、一人で起業するにはピッタリだと思い、その場所を選びました」
紆余曲折を経て2012年、大淀中の梅田スカイビルにほど近い場所に、クラフトビール専門店のビアカフェ『CRAFT BEER BASE』が誕生した。
正しい品質管理は、自分たちで造って伝える
開店した当時は、FacebookなどのSNSが流行り始めた頃で、その情報発信のつながりで旧知の知り合いも店を訪れてくれた。店は当初、谷氏一人で始める予定だったが、ちょうど飲食店を始めようとしていた知り合いが、キッチンを担当することで協業することになった。立ち上げたばかりの店舗で、自分たちの給料を確保することはとても厳しかったが、次第に「ここで働きたい」という人が増えてきたという。
「そんなにビールが好きならおいでよ、と招き入れてきましたが、そうなると手狭になるし、店舗も増やさなきゃいけない。それなら10年後の未来に向けた事業計画、というか未来予想図を描いてみようと思いました」

その頃には横のつながりが増え、いろいろな店舗やインポーターの担当者と意見を交わす機会が多くなった。その中で話題として多かったのがビール流通の品質管理の方法についてだったという。
「海外とは違い、当時の日本には品質を評価する機関が少なく、みんながどうやったら一番美味しいのか、手探り状態で管理していたのが実情です。中立の立場で提言する存在がないと、市場としてきちんと成熟していかないなと思いました」
ビアジャッジの経験を積みながら、自分たちで選んだビールを販売する。その延長線上で、いつか自分たちで自分たちのビールを造ると決めた。
いまできることをやる、このチームは強い
10年後の計画よりも早い2018年に醸造部門と併設したブルーパブを立ち上げ、翌年に自社醸造ビールの販売を開始した。そして2021年には、約500種類のボトル・缶ビールの販売、ビアパブ、醸造所を一つにした『CRAFT
BEER BASE MOTHER TREE』を開店させた。
「醸造するまでは、ビールのセレクトショップという感覚だったんですね。目利きとして出来上がったビールを一番いい状態でお客様に提供するプロです。
ところが造り手になってから、ピルスナーモルトにもいろいろな種類や原産国、メーカーがあるなど、初めて知ることも多かった。この時の学びがビール造りの幅を広げてくれたと思います。一方で地元の人から『これは大阪のビールなんやね』って言われるようになって、それじゃあ自分たちが造る“大阪”のビールってなんだろうと考えているうちにコロナが来て…。世の中が一斉にストップしてしまいました」

当時CRAFT BEER BASEでは、樽での販売のみだったため、流通用の商品化はしておらず、ネット通販にも対応していなかった。そんな中、醸造ディレクターがありあわせの機材でボトリングマシンを手作りしたという。
「これがとても優秀なマシンで、つい最近まで活躍していたんですよ。それも自分たちのビールの質を熟知していたからこそできたことで、自分たちの専門性に感謝しました。それがきっかけでスタッフの気持ちに火がついて、各自が自分たちがいまできることをやろうと。ネットで配信をする人、ネット通販に取り組む人、YouTubeを始める人…。その様子を見ていて、このチーム、強いなって心底思いました」

谷氏自身も「クラフトビールの灯を消さない」をテーマに、20社ほどのビアパブとタッグを組んでクラウドファインディングに挑戦した。また、思い切って小さな店舗を閉店させて、MOTHER
TREEに人も機能も集約した。地元の人たちも、応援とともにビールを買いに来てくれたという。
「地元の人たちと助け合うなかで、自分たちの役割を考えたときに、ビールを通じて文化を発信する基地を作って大阪の地ビールになろうと思いました。ビアジャッジとして世界で日本を代表する目線と、海外から仕入れる知識を持って、大阪をもっと楽しめる、大阪の人たちに愛される場所になればいいなと思います」
それは商品化が進み、海外での展開も視野に入れている、ということだろうか?
「究極を言えば自分たちのビールは地元で売れたらそれでいいと思っています。この街に来て飲むビールとして、この街の自慢になれば嬉しいし、お土産にもしてもらいたい。誰が来ても自信を持ってお出しできる、とことん地ビールでありたいと思っています」
美を追求する、とことん地ビールでありたい
CRAFT BEER BASEが造るビールは、基本に忠実なものもある一方で、クラフトビールのなかでもかなり独創的なものもある。
「うちの醸造長は、立ち上げ初期からのスタッフで『僕たちすべて一から始めましょう』と、一緒に醸造ラボを立ち上げてくれました。私たちは基本的に誰かに師事することはなかったので、化学的な考え方や菌に対する専門知識などはまだ未熟です。ただ、基本に忠実なことで過去は紐解けるけれども、それだけでは新しいものを生み出すことはできません。知識と技術、そして感性とアート性を合わせて、自分たちが美しいと思うもの、新しいと思うものを造ることが私たちのテーマです」

それを形にしたものが醸造長独自のブランド「醸馥 Olfactory works」だ。香りと嗅覚にフィーチャーした独創性の高い仕上がりになっている。
「同じビールというカテゴリーであっても、みんな同じである必要はありませんよね。レシピが同じでも環境が変われば味も変わるくらいですから、一つひとつがみんな違ってみんな良い。それを認め合えるのがクラフトビール業界の良さであると思っています」

第三次クラフトビールブームと言われ、多くのクラフトビールが誕生している。それでも谷氏の当初からの信念は変わらない。
「基本的なビールの知識や品質管理やサービングなど、やはりビールにとって正しいスタイルをきちんと再現することが私たちの使命です。ビール好きの基地、ビールの基盤となる役割を担う、その思いを『CRAFT BEER
BASE』の社名に込めています」
社名のロゴデザインは、“C(クラフトビール)”の真ん中の点(存在)となって、ビールで乾杯している場面を王冠に見立ててイメージしたという。そんな風に、競合という壁を越えて相互に学び合いながら業界を盛り上げていくことが谷氏の願いだ。

「コロナで世の中が断絶されたとき、多くの人が孤独感を身に染みて感じたんじゃないかと思うんです。ただでさえ都会のコミュニケーションって、あるようでないというか…。コミュニケーションの一つとして、ビールはそこにも一役買える。誰かの心の拠り所になって、『おかえり』って言葉をかけられる場所になればいいなと、『MOTHER TREE』という名前を付けたんですよ」













